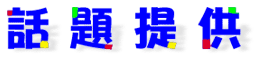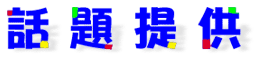最近、博物館の自然科学教室に参加してくれた子どもたちに「知ってる化石のなまえ教えて!」と聞くと「アンモナイト!三葉虫!恐竜!」という答えが返ってきました。一般に化石ときいて思い浮かぶのはこのあたりでしょうか。これらの化石は、生きものの骨や殻などの硬い部分が地層中に残されたもので、「体化石」と呼ばれます。化石になった太古の生きものたちも食べたり、歩いたりしていたので、このような生活や活動の跡も地層中に残されることがあります。これを「生痕化石」と呼んでいます。
生痕化石を調べると
化石は、かつて地球上に棲(す)んでいた生きものがどんな生きものだったかを知るために調べられます。生きものの姿形だけでなく、どんなふうに暮らしていたのかも調べます。骨や殻の化石を調べてもその生きものが何を食べていたのか、どんなふうに動いていたのかを正確に知ることはできません。そこで、生活や行動に関する情報を記録している生痕化石を調べると、さらに詳しく過去の生きものがどんな暮らしをしていたのかがわかります。また、生痕化石は、今生きている生きものがどんな生活をしているのかを明らかにするのにも役立っています。たとえば、深海底にもぐって生活している生きものを調査することは技術的にかなり大変なことです。しかし、過去に、今生きている生きものと似たものがいて、深海底に生活の痕跡を残し、それが、地上で見ることのできる地層中に保存されていると簡単にじっくりと調べることができ、深海底の生きものの生態を知るためのヒントになるのです。
生痕化石いろいろ
 |
写真1:鳥の足跡化石
(古代三紀始新世 アメリカ) |
 |
写真2:ウニのはい跡化石
(第四紀更新世 石川県金沢市) |
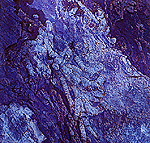 |
写真3:巣穴の化石
(白亜紀 愛媛県宇摩郡土居町) |
歩き跡
恐竜やカニなどの足跡化石があります。足跡化石からは、足跡を残した生きものの大きさや歩く速さを推定することができます。また、いくつかの歩行跡が同じ方向にならんで適度な間隔をもっていると、群れで行動していたと考えることができます。
はい跡
ウニや巻貝のはい跡などがあります。海底や底質中をはう生きものによって残されます。
住まい跡
エビやカニ、ゴカイなどの巣穴などがあります。また、アンモナイトの化石で円形のくぼみがあるものが産出しています。このくぼみはカサガイの仲間が付着していた跡と考えられています。
食べ跡
二枚貝の化石で小さな穴が開いているものがあります。この穴は、ツメタガイのような肉食性巻貝が二枚貝を食べるために開けた穴です。
その他に、排泄物(はいせつぶつ)(フン)の化石(写真4)や胃石(写真5)、骨折のようなケガや病気の跡などもあります。フンの化石からは、食べていたものの骨片やうろこが見つかることがあり、何を食べていたのかがわかります。
 |
 |
写真4:恐竜のフン化石
(ジュラ紀 アメリカ) |
写真5:恐竜イグアノドン胃石
(白亜紀 イギリス) |
愛媛の生痕化石
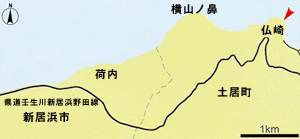
図1:仏崎の位置図 |
愛媛県では、宇摩郡土居町仏崎の海岸で巣穴の化石がみられます(図1)。この化石は、中生代白亜紀(約7000万年前)の和泉層群の砂岸層中にあります(写真3)。仏崎から荷内にかけての海岸では、波がつくった規則的な峰と谷からなる構造・漣痕(れんこん)(リップル)が観察でき、白亜紀に絶滅した二枚貝・イノセラムスなどの化石も見つかっています。
※このあたりは干潮時でないと観察することはできません。
(自然研究科 学芸員 山根勝枝) |